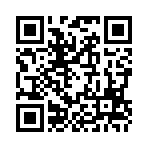事務所からのお知らせ
長野県弁護士会主催の講演会開催についてお知らせ致します。
今年度は,基本的人権を守り発展させるうえで大きな役割を果たす
憲法の視点から「同性婚,選択的夫婦別姓について」をテーマに
ご講演いただきます。
また,新型コロナ感染拡大が懸念される状況を踏まえ,
場所を選ばず多くの方々にご参加いただけるよう「Zoom配信」での
開催を企画いたしました。
多くの皆様のご参加をお待ちいたしております。
どうぞお気軽にご参加ください。
【テ ー マ】憲法の視点で「結婚」を考える
-同性婚、選択的夫婦別姓に関する裁判を素材に-
【講 師】東京都立大学法学部教授(憲法学) 木村草太先生
【日 時】2022(令和4)年2月19日(土)午後2時~午後4時まで
【参 加 費】無 料
【参加方法】①長野県弁護士会ホームページ(
http://nagaben.jp/)から
(弁護士会の活動→イベント→憲法シンポジウムウェビナーはこちら)
②「憲法シンポジウムパンフレット」記載のQRコードから
(QRコード読込→憲法シンポジウムウェビナーはこちら)
・①か②いずれかの「憲法シンポジウムウェビナーはこちら」から
オンライン配信にご参加いただけます(上限500名)。
・ご参加にあたっては下記の「※」をご確認ください。
 (憲法シンポジウムパンフレット)
※パンフレット記載のQRコードをご利用ください。
※その他注意事項等
(憲法シンポジウムパンフレット)
※パンフレット記載のQRコードをご利用ください。
※その他注意事項等
Zoomウェビナーへの参加にあたり,Zoom上でお名前とメールアドレスの入力が必要になります。
Zoomについては,Zoomサービス規約の内容をご確認いただき,同意の上でご利用ください。
当日,何等かの理由で通信が中断し復旧困難となった場合(10分以上配信不能)には,
やむを得ずシンポジウムを中止する可能性があります。
視聴者のPC環境・通知状況等の不具合について,当会では責任を負わず,Zoomの利用方法等に
ついてのサポート対応等も行いかねますので,予めご了承ください。
配信内容の撮影・録画・録音は禁止致します。
※個人情報の取扱について
本イベントはWeb会議システムであるZoomを利用して開催します。
Zoomの利用規約やプライバシーを確認・同意の上でご利用ください。
なお,長野県弁護士会及び共催団体は,参加者が本イベントのZoom接続時に
入力した個人情報(氏名・メールアドレス)については,取得致しません。
事務所からのお知らせ
平素より当事務所業務にご協力を賜り誠に有難うございます。
当事務所は
【令和3年12月24日(金)から令和4年1月5日(水)まで】
年末年始休業を頂戴いたします。
法律相談は予約制となりますので、法律相談をご希望の方は、
まずは、お電話でご予約くださいますようお願いいたします。
お悩み事やお困り事など、ひとりで抱え込まず、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
皆様におかれまして、良いお年のお迎えでありますよう
祈念いたしております。
令和3年12月吉日
内村法律事務所
弁護士 内村 修
事務員 小林直美
事務所からのお知らせ
令和元年10月1日からの消費税増税に伴い、弊所でお受けしている相談料の
消費税は、8%から10%に引き上げを行います。
令和元年9月30日までの相談料は10,800円(税込)、
令和元年10月1日以降の相談料は11,000円(税込)となります。
法律相談をご希望の方は、先ずはTel:026-235-0203(内村法律事務所)まで
お電話を。
事務所からのお知らせ
高齢化の社会経済情勢の変化に対応するため,約40年ぶりに
相続に関する法改正が行われました。
この法改正は,2019年(平成31年)1月から2020年7月に掛けて,
段階的に施行されていきます。
その第一号となる「自筆証書遺言書」の作成方式の一部緩和が,
2019年(平成31年)1月13日に施行されました。
また,法務局で自筆証書遺言書を保管する「遺言書保管法」は,
2020年7月に施行されますので,
作成された大切な遺言書が紛失するなどといった
トラブルを回避することも,将来的に可能になります。
生前の贈与を含め,相続に関する紛争を予防することは,
決して難しいことではありません。
今回の法改正は,多くの方々に「遺言書を作成しよう」と
感じていただけることによって,相続をめぐる紛争予防へと
繋がることが期待されています。
これまで,遺言書の作成を躊躇されていた方は,
これを機に,是非,遺言書の作成に取り組まれてみては
いかがでしょうか。
遺言書作成までの手順など,ご心配ごとは,
お気軽に法律の専門家にご相談ください。
【法改正前後の比較】
改正前 改正後
遺言書全文 全て,自書(本人が書く) 全て,自書(本人が書く)
財産目録 全て,自書(本人が書く) パソコン作成が有効
通帳コピー コピーの添付は無効 コピーの添付が有効
【メリット】
①「財産目録」などといった添付書類の作成方式が緩和され,
負担が軽減された。
②自書でない財産目録には,遺言者本人の署名(自書)と
押印をしなければならないので,偽造も防止できる。
事務所からのお知らせ
新年あけましておめでとうございます。
平成最後の年が始まりました。
ごく普通に日常生活を送っているにも関わらず,
様々なアクシデントやトラブルに見舞われ,
悩み、困難をお抱えの方は少なくありません。
当事務所では、ご相談にお見えになる方の心に寄り添い,
ともに考えることを大切にして、弁護士業務に臨んでおります。
本年も皆様にとってお健やかで、
よりよい一年となりますよう力添えして参ります。
内村法律事務所
弁護士 内 村 修
事務所からのお知らせ
8月13日(月)から16日(木)まで,夏季休暇をいただきます。
法律相談は,予約制で承っております。
ご希望の方は,事前にご予約いただきますようお願いいたします。
内村法律事務所
電話:026-235-0203
お気軽にお電話ください。
記録的な暑さが続いていますので,
ご自愛くださいませ。
事務所からのお知らせ
早いもので,平成29年が終わりを迎えようとしております。
お陰様で,平穏に今年も業務を行えましたことを,
有り難く感じております。
当事務所の年末年始休業は,以下のとおり
予定させていただきました。
なお,法律相談は予約制でお受けいたしております。
大変恐れ入りますが,事前にお電話で予約の上,
ご来所くださいますようお願いいたします。
〈年末年始休業〉
平成29年12月29日(金)から平成30年1月4日(木)まで
新年も,よろしくお願いいたします。
どうぞ,佳きお年のお迎えでありますように。
弁護士 内村 修
事務所からのお知らせ
認知症などで判断能力が低下した方の生活支援のための「成年後見制度」は,
社会の高齢化に対応出来るよう,介護保険制度とともに平成12年(2000年)4月に
始まった制度です。
裁判所の公表資料によると,平成27年に申し立てをされた方を対象に行った
「申立ての動機別件数」調査では,
①「預貯金の管理・解約」と「介護保険の契約」が6割程度
次いで
②「身上監護」
③「不動産の処分」
③「相続手続き」
と,続いています。
特に,施設入所にあたり介護の費用のため,預貯金を解約しなければならない等,
必要に迫られて申立てに至る方が多く見受けられるようです。
日頃の備えとして,ご本人が元気なうちに,年金の収入,預貯金,不動産,
有価証券等といった財産について,「確認し合う」会話は,
いざという時の大切な備えになるようです。
お困りの方,ご心配のある方は,「成年後見制度」をご検討されてみては
いかがでしょうか。
法律の専門家から,制度の内容やポイントなど,より詳しくご説明させて
いただきます。
お気軽に,お電話ください。
事務所からのお知らせ
交通事故のトラブルは,早めの対処が大切です。
不運にも,事故に遭遇されてしまった場合は,人損,物損問わず,
まず,警察に通報して,その事故処理を受けましょう。
また,相手の方との交渉が難航しているなど,お困りの時は,後々の
トラブルや二次被害を回避するために,法律の専門家に相談することも
選択肢のひとつです。
特に,最近は,任意の損害保険特約に「弁護士費用」を組み込まれている
損害保険が増えていますので,ご加入の保険で「弁護士費用」を
負担してくれます。これにより,自己負担なく,弁護士が代理人となり,
相手方との示談交渉を進めることが可能になります。
過失割合,膨大な修理代請求など,少しでも疑問に感じる事案は,
法律の専門家に,お気軽にご相談ください。
事務所からのお知らせ
年内は,12月28日(水)の相談を最後に,休暇に入らせていただきます。
ご相談のある方は,事前にお電話にてご予約の上,ご来所くださいますよう
お願いいたします。
内村法律事務所
弁護士 内 村 修
事務所からのお知らせ
ご親族の問題(相続や遺産分割)
相続問題や遺産分割については、生前には気にならなかった問題もご親族が亡くなられた途端問題が露呈し、複雑化することも大いに考えられます。
財産を分ける前に意思を遺す方法、また実際に分ける際に争いになった時に解決する方法があります。
ここでは遺言書や相続分、遺産分割協議について説明したいと思います。
遺言書
まず、遺言書は、法定相続分ではなく自分の思いを反映する手段として考えられます。
相続は遺言書がある場合には遺言書の通りに、ない場合には法定相続分にしたがって分けられます。したがってあらかじめ遺言書の作成をしておくことが願いを叶える手段として考えられるでしょう。
遺言書は次のものがあります。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つです。
自筆証書遺言
遺言をする人が自分の手で書いて行う遺言です。遺言の全文を手書きし、遺言の日付と遺言をする人の氏名を書いて押印します。これらの記載が一つでもかけていたり記載が不完全な場合には、有効な遺言にはならなくなってしまいます。また、他人に代筆してもらったり、パソコンで作成した場合などにも無効になります。
秘密証書遺言
遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印してこれを封筒に入れ、文書に用いた印で封印し、これを公証人に提出して作成します。
公正証書遺言
遺言をする人が、2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、筆記の正確性を承認した全員が署名押印して作成します。
ただ、これらはすぐに開封して相続を開始できない場合もあります。例えば公正証書によって作成された遺言を除いては、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、速やかに家庭裁判所に提出し、その検認を請求する必要があります。
遺言の内容によっては、遺言執行者の選任が必要な場合もあります。
遺言書の作成でご不安があるような場合には、弁護士に相談したうえで作成することもできます。有効な遺言書の作成をすることによってご意思を残せる手段を利用しましょう。
もっとも、遺言書で特定の相続人にのみ相続させる場合にも、他の相続人には遺言書によっても侵すことのできない一定の割合の相続分(これを遺留分と言います)がありますので、その点には注意が必要でしょう。
法律で決まっている相続分(法定相続分)について
遺言書等が残されていない場合には、法律で規定された割合で分けられます。これを法定相続分といいます。
まず、配偶者は常に相続人となります。ちなみに被相続人と離婚した場合はここにいう配偶者にはあたりません。次に第1順位の相続人は被相続人の子供です。子供は両親が離婚したとしても相続権を失いません。
子供がいない場合には、被相続人の親(直系尊属)が第2順位の相続人となります。これもいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
実際に遺産を分けるときに話がまとまらない場合
この場合、離婚のような家族の話し合いと同様、家事調停を利用する事が出来ます。調停の手続を利用して話し合いをし、合意ができれば成立となります。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して審判で強制的に裁判所が決めます。
■債務整理
まず、お金を複数の業者からたくさん借りている状況を多重債務と言います。借りては返し、という状況がその典型です。
返済が苦しい状況であるならば債務整理をする必要があります。
債務整理の方法としては4つの種類があります。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産です。以下、それぞれの方法の内容や特性について説明します。
任意整理
任意整理とは、裁判所を通さないで直接金利を減らしたり免除してもらったり、分割払いの金額を減らしてもらうように交渉する手続です。月々の金額を減らして少しずつ返していきたいという希望がある場合にまずこの方法を考えます。
特定調停
特定調停とは、任意整理のような交渉を裁判所の調停手続を利用して行う手続です。裁判所への申立手数料は1社あたり500~1000円程度の低額で行うことが可能です(弁護士費用は別途かかることに注意が必要)。しかし、調停手続のため、出頭の回数が多いという点で依頼者自身の時間的拘束が多いことがデメリットとしてあります。時間の都合がつきにくい方には不向きかもしれません。
個人再生
個人再生とは、継続的に一定の収入が得られる見込みがある方で、5000万円を超えない借入について最低100万円以上を返済することを約束し、残りの債務を免除してもらうという民事再生手続です。住宅ローンのついた住宅をお持ちの方で、家を失わずに債務整理したいという方にはメリットのある方法であるかと思います。
自己破産
これが一番皆さんご存じの手段かもしれません。破産も債務整理の一種です。自己破産とは、破産開始決定が出て免責許可決定が下りると、残っている債務が全額免除になるという制度です。
大きな効果が得られる分、デメリットも大きい手続です。手続の最中は職業や転居の制限があったり、官報に破産したことと住所と名前が記載されたりと、破産したことを知ろうと思えば誰でも知れてしまうという状況下に置かれます。また、数年間は借り入れができません。最終手段として用いられます。
しかし支払が一切不能となってしまった方や、年金収入のみの高齢者の方には逆にメリットも多いです。
以上、概要を説明しましたが、いずれの方法が良いかはお客様の経済状況などによっても異なります。方法については当所の弁護士と相談が必要です。
ただ、どの方法でも信用情報(いわゆるブラックリスト)に載ってしまうことは念頭に置いておいてください。
■過払金返還請求
最近テレビでも過払い金返還請求が多く取り上げられています。払いすぎていた分を返してもらうというのがこの制度なのですが、何をもって払い過ぎと言うのでしょうか?
利息制限法という法律に、以下の通り借入金額に応じた金利の上限が決められています。
元本が10万円未満の場合・・・・・・・年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合・・・・年18%
元本が100万円以上の場合・・・・・・年15%
まず今のご自分の借入の金利がどのくらいなのか確認してみましょう。もしこの上限金利を超えているようであれば、超過部分の契約は無効なので、超えた部分を返してもらうことができます。この超えた部分というのが「払い過ぎ」であり、これを返してもらうのが過払金返還請求というのです。
払い過ぎていた部分は順次元本に充当し引き直し計算をすると、結果元本が減ることになります。充当して計算してみると、もう完済している可能性も十分考えられるわけです。それでもなお払い過ぎているようであれば、残りを返せと言うことができます。お金の問題として一番多く寄せられるトラブルはやはり借金の問題でしょう。
過払金返還請求は本来、不当利得返還請求権(民法703条)という権利に基づいて行うものです。すなわち、払う必要のない余計なものを払ってしまい、相手はそのようなお金は受け取る立場はないにもかかわらず受け取ってしまっているからこそ、返せと言えるのです。